
2018.12.12
一歩を踏み出せる、そんな場所
学校法人シュタイナー学園 ニュースレター
VOL.49 2018.12.12
共働き家庭が増える中、仕事を持ちながら子どもを通わせることはできるのか、という質問をいただく機会も増えています。今回は学園保護者の話を通し、お母さんの働き方の形や学園・藤野での生活のご紹介をしたいと思います。
学園2年生保護者のBさんは、娘さんの小学校入学を機に都心から藤野へと移住しました。藤野に越すまで、週4日会社で中国語関連の仕事、週1日太極拳の教室を開催していたそうです。Bさんがシュタイナー教育を知ったのは、まだ子どもを持つ前のこと。
「ユネスコ関連の団体で教職員の国際交流の企画や運営を通して、子どもの教育を考える職についていた時、シュタイナー学校の冊子を見てこんな学校があるんだな、と思ったんです。もともとは、中国語の専門学校を卒業し中国のIT企業に就職したのですが、ひたすら利益追求をする働き方に違和感を感じました。専門学校時代からずっと太極拳を習い、研修に中国に行ったりもしていたのですが、先生に『もっと上手になりたかったら人に教えなさい』と言われたこともきっかけになり、働き方を変えようとユネスコ関連の非営利団体での非常勤職員と自分の教室を開くという働き方にシフトしたんです。」
数年後子どもを授かったタイミングで仕事を辞め、夫婦でどんな教育をしたいか話した時、以前聞いたシュタイナー教育のことを思い出したBさん。本を読み、これは自分が求めていた教育だと、家庭の中で取り入れるようになりました。
「とはいえ、メディアを避けること、自然素材のおもちゃに触れること、食べ物に気を使うことくらい。東京では夫婦共働きがよいだろうと、産後しばらくして再び就職し、子どもは保育園に通っていました。週4日、非常勤の会社勤めで翻訳やWEB企画の仕事と週1日の太極拳の教室。そんな生活がしばらく続きました」
転機は子どもの成長だったといいます。
「都心の家は狭く、もっと広い場所でのびのび暮らしたいと探すうちに、高尾あたりだったら環境もいいし中央線で仕事に通えそうだ、と思ったんです。そうしたら近くにシュタイナー学園があることを知って。同時期に夫の恩師であった高校時代の先生がアメリカ・サクラメントのシュタイナーカレッジの教員養成を受けていて、その体験レポートが届いたんです。読んで感銘を受けましたし、何か導かれているように感じ、学園の公開講座に会社を休んで参加しました。ちょうどAWTCというアジアのシュタイナー学校の先生が集まる交流会議の期間に開催された公開講座で、『世界中にシュタイナー学校は増えているのに、なぜ日本は増えないと思いますか?』という問いを投げられたんです。以前教育関係の仕事をしていたので、日本は学校を作る制度がとても厳しいことを知っていましたし、縦社会で管理教育の社会にその原因があるのではないかと思った時、シュタイナー教育は今本当に必要な教育なんじゃないかと、心が突き動かされてしまったんです」
その後、家族で何度も学園に足を運び、入学を決めたBさんでしたが、当初仕事は辞めざるを得ないと考えたといいます。それでも10年続けていた太極拳の教室は誰かに代わってもらうことのできない大切な仕事でした。
「都心の教室に行って帰ってくると、子どもの朝の送迎と帰宅時間に間に合わない。担任の先生に相談してみると『送迎支援』という保護者のかわりに子どもを送迎してもらえる制度と学童を使えることになり、教室を続けられることになりました。その上会社に子どもの教育のため移住することを伝えると、その熱意を応援したい、と言っていただき、在宅で週3日ほど、無理のないペースで続けさせてもらえることになったんです。こちらの熱意が伝わると変化していくことってあるんだな、と思いました」
移住して一年半、藤野でも太極拳を教えるようになったBさん。太極拳を教えながら畑を始めたり学校の係をやったりと、忙しくも充実した時間の中で、仕事以外のことへの関心も高まっていったと言います。そしてこの9月には在宅の仕事を辞める決断をしたそう。
「ここに来る前は“暮らし”というものになかなか気持ちがいかなかった。何かに導かれるようにシュタイナー教育と藤野に出会いここにやってくると、求めていたこと、やりたいと思うことがたくさんありました。仕事と同じくらい暮らしも大切にできる。今後は、ここで出会った新しい『何か』を、また自分の仕事にできるんじゃないか、とそんな予感もしているんです」
仕事を続けることは可能な環境だったけれど、一つの区切りをつけたというBさん。シュタイナー学園、そして藤野という場所は、教育・仕事・暮らし、その一つ一つが分断することなく繋がり、お母さんにとっても新しい一歩を踏み出す勇気をくれる、そんな場所なのかもしれません。
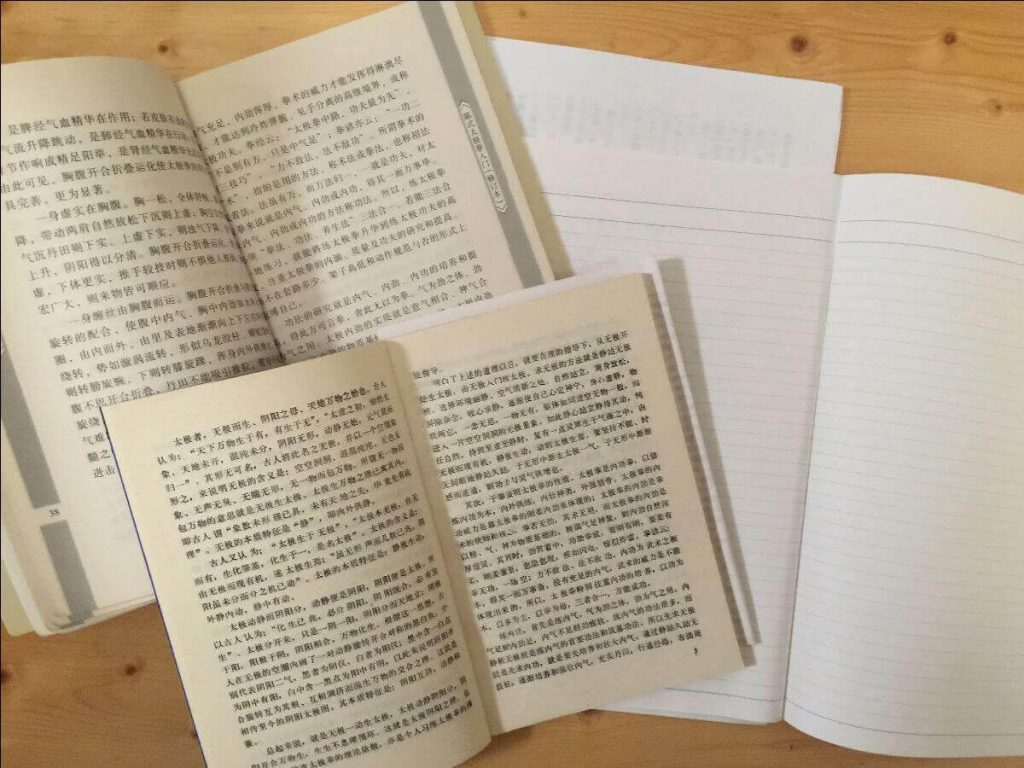
ライター 中村暁野

